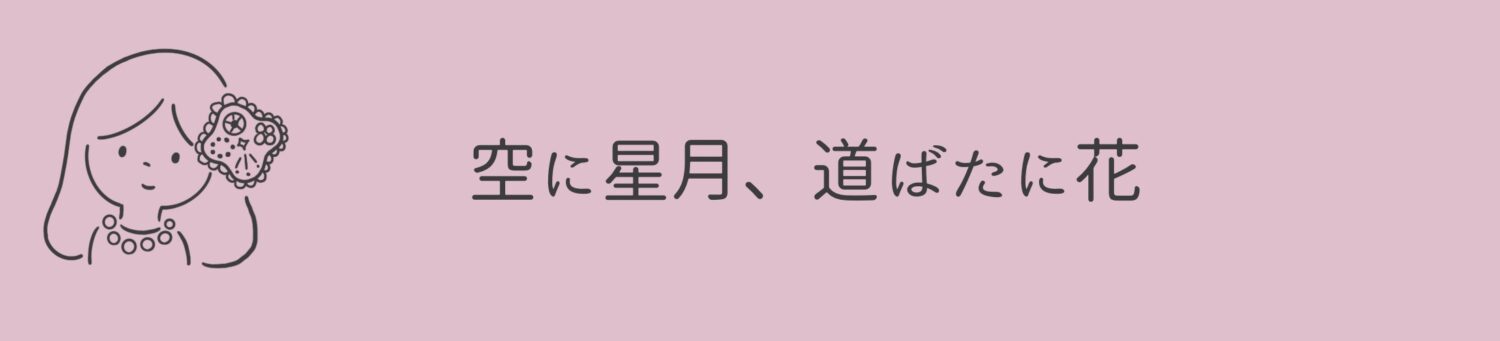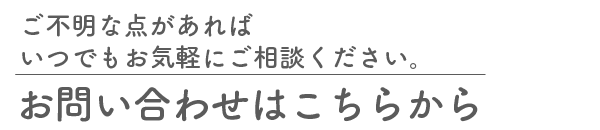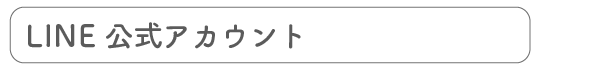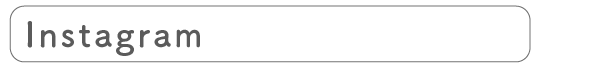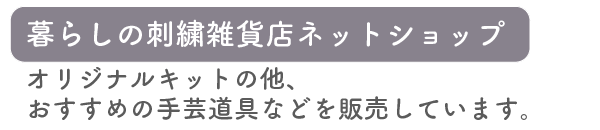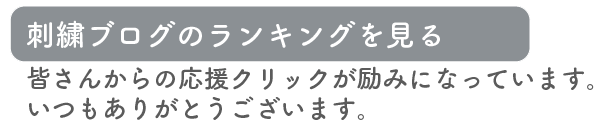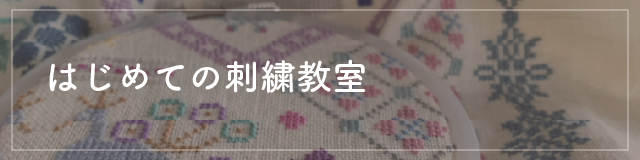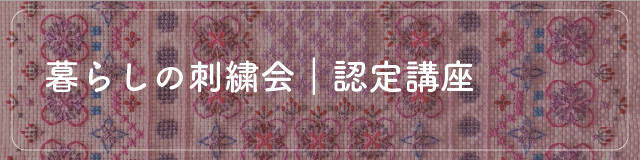はじめに


この記事は、私が刺繍を仕事にした経緯と、そこから今までの歩みを振り返る連載の第1回です。素敵なご縁や出会いをきっかけに少しずつ広がっていった仕事の過程を、1話につき2〜3分で読めるボリュームにまとめています。
スタートは2011年。年少さんと2才だった娘たちを育てていた私、32才。ここから始まります。
やっと"私の時間"をゲット!! 待ち望んだ「下の子の入園」
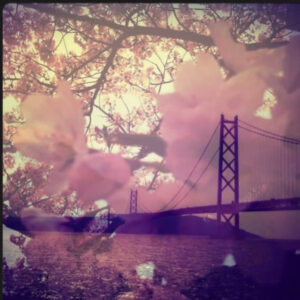
当時の携帯カメラのアプリで写真を重ねる加工など楽しんでいました。やっぱりお花が好き!
娘たちが幼稚園に入園するまでは、限られた時間をできるだけ一緒に過ごしたいという思いから、親に預けることはほとんどありませんでした。2歳差の姉妹と、毎日どっぷりと向き合って過ごす日々です。
預けることはなくても、母は週に何度も車を出して、私たちを舞子のアウトレットや元町へ連れて行ってくれました(当時は神戸市垂水区に住んでいました)。ウィンドウショッピングをしながらベビーカーを押して歩き回り、娘たちがお昼寝を始めたタイミングでカフェに入る――それが定番のコースでした。

制作途中の写真しか見つからないのが本当に残念!
長女の入園と同時に、園のスモックにキキララちゃんみたいな世界観で娘たちが遊んでいるような模様の刺繍を施したり、小さなバッグやチュニック、キュロットを縫ったりして、針仕事を楽しむ時間が少しずつ増えていきました。

手作りのチュニック。洗濯物たたみ。
このときの刺繍は、単に華やかに見せたくてするものではなく、「娘の持ち物を、自分の手で作ってやりたい」という気持ちから始めたものです。いわゆる“手作りらしい手作り”として、その子のためだけに形にすることが、当時の私にとって大切でした。

手作りのエプロンで子ども包丁デビュー
価値観を形づくった伯母の影響

娘たちが寝落ちてくれたら私の刺繍時間! 寝違えたら可哀想…と角度を直そうとしてあげたら起きてしまうこともしばしば。
こうして自然に針を手に取る時間が増えていく中で、私の中には二つの「当たり前」がありました。ひとつは「ある程度の大人になれば、暮らしの布小物は当たり前のように手作りするようになるものだ」ということ。もうひとつは「着物は自分で着られて当然」ということです。
この背景には、私の伯母の存在がありました。四姉妹の長女として、和裁でも着付けでも花嫁衣装まで仕立て、その花嫁衣装を着付ける仕事までできる腕前の人でした。浴衣や座布団、園バッグや上履き入れ、お人形まで、手作りらしい手作りの品を私たちに仕立ててくれました。それも私を含めた9人のいとこ全てにです。
別に「そうなりなさい」と母や伯母に言われたわけではないのに、そんな姿を見て育った私は、「作れるものは作るもの」「着物はどこかで習い、大人になれば自分で着られるもの」と自然に、そして強く思い込んでいました。
まさに「昭和の人間に育てられた私」でした。私は昭和54年生まれで、その価値観を疑うことなく受け継いでいたのです。

母が買ってくれた水着。かわいかったなあ。そして次女の腕には謎のシール。
第2回へつづく
この頃の私は、ただ自分や家族のために趣味や家事として針を持つ日々を過ごしていました。けれど、思いがけない出会いが、のちに刺繍を仕事へと導いてくれることになります。
-

-
刺繍と私の物語02|初めて売ったのは着物のための刺繍小物
こんにちは。刺繍作家のアズママイコです。 「刺繍と私の物語」第2回です。 ★この連載の目次ページはこちら 着付けのお稽古へ シンクロ寝。しつこいようですが、娘たちが寝たらとにかく刺繍時間 ...
続きを見る
刺繍と私の物語
教室のご案内
・刺繍教室の通い方:おけいこ通いの始め方
・最新のレッスン案内:教室からのお知らせ
・ご予約の流れ:ご予約について
・刺繍を仕事にする:認定講座のご案内