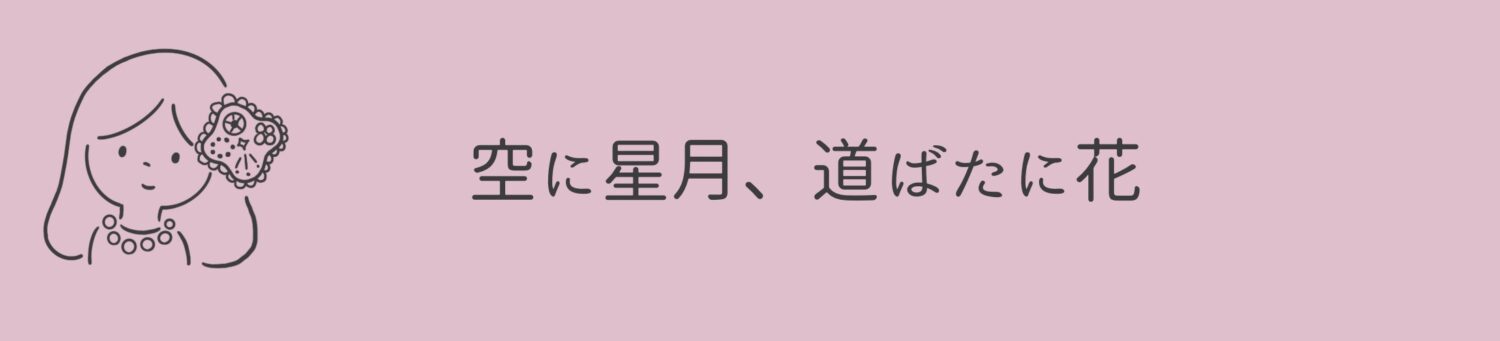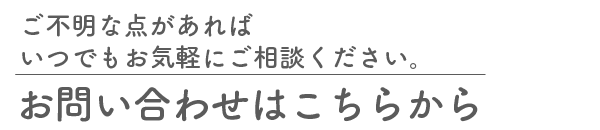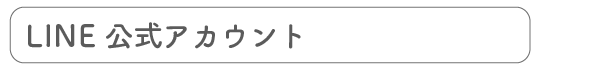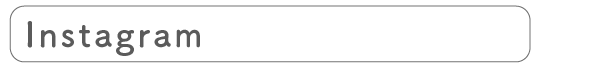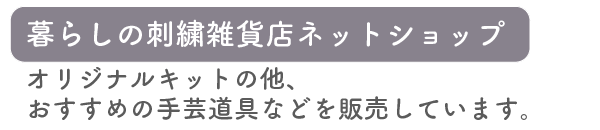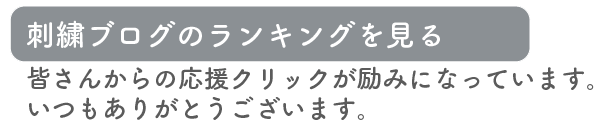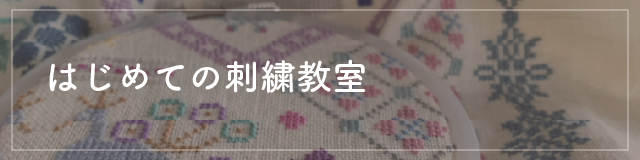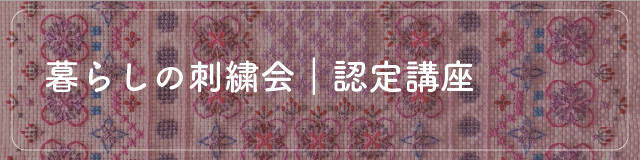はじめに
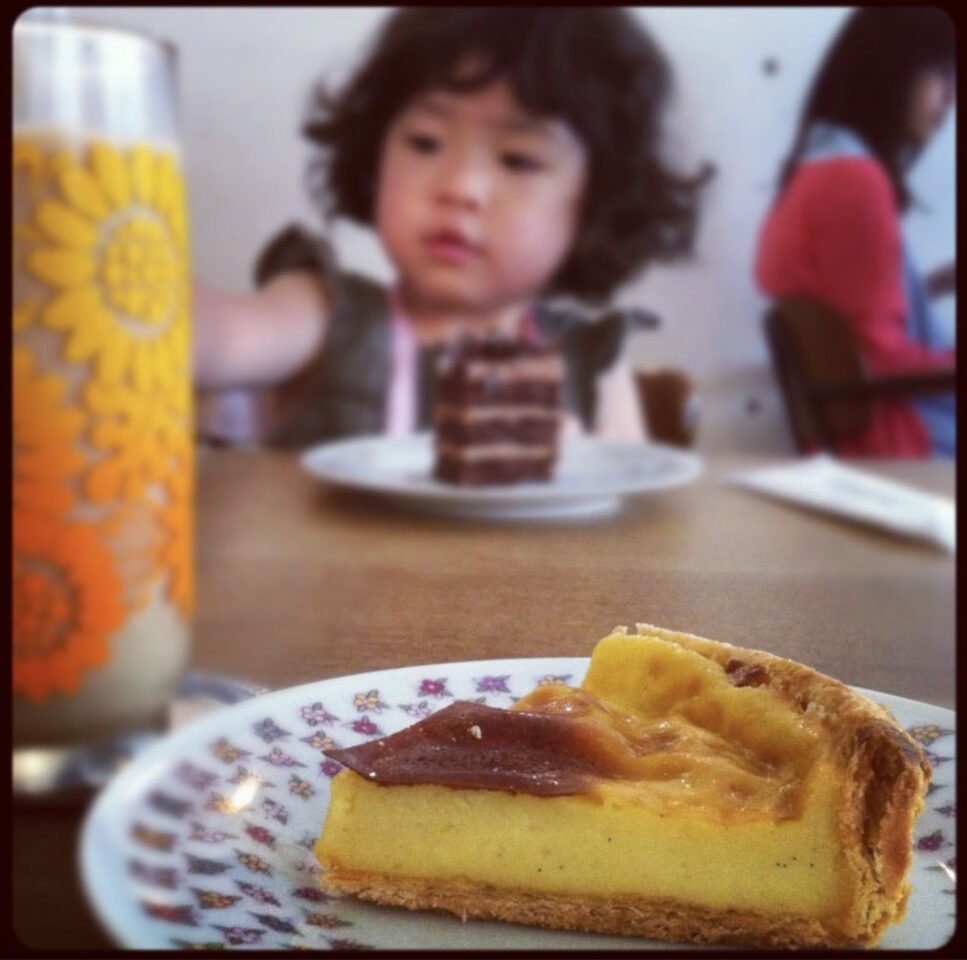
こんにちは。刺繍作家のアズママイコです。
「刺繍と私の物語」第5回です。
初めてのレッスンは着物屋さんでの刺繍半衿ワークショップ
2012年、私は刺繍教室を始めました。きっかけは、着物小物を納品していた中崎町の着物屋さんでのワークショップ企画。リネンにアウトラインステッチで伝統紋様(七宝つなぎ)を刺繍して半衿を作るという内容でした。どんなふうに準備して、どんな人たちが集まってくださったのか、細かい記憶はもう薄れてしまいましたが、そこが私にとって「教える」ということの最初の場となったのは確かです。
刺繍を仕事にする、を考える

Instagramが消えてしまったのでこの頃の作品写真がとにかくないのです…ここでは代わりに、当時の園エプロンに私が描いたお花の写真を
着物屋さんとのお仕事は、収入のためというよりも「認めてもらえる嬉しさ」や「作る楽しさ」が大きな原動力でした。けれど下の子も入園して、私自身も何か“仕事らしい仕事”をしなくてはと思うようになったのです。主婦としての立場はそのままに、しっかり働いて家計にも貢献したい——そんな思いが強くなったとき、夫から魔法のような言葉をもらって、私は「教室をやってみよう」と一歩を踏み出すことができたのです。
大阪の刺繍教室の始まり

この写真だけはありました。「ましかく」に通じていくデザインですね。
その少し後、2012年6月には初めての自宅レッスンを開きました。娘の幼稚園で知り合ったママ友さんが「刺繍を習ってみたい」と言ってくれたのがきっかけです。記念すべき初回は2人のお生徒さんをお迎えし、「ニードルブック」と、あとはリクエストをいただいた「ティッシュケース」で刺繍デビューしていただくことにしました。色合わせは、まずそれぞれに好きな色や使いたい色をいくつかピックアップしてもらい、それをもとに私がバランスを見ながら配色しました。もちろん「すべて自分で決めたい」という方にはお任せしたいと考えていましたが、配色をすべてご自身で決めたいという方はここからしばらく、ほとんどいませんでした。私は好きな色を挙げてもらい、それを足したり引いたりしながら小さな世界を整えていくのがただただ楽しく、色に悩むことはほとんどありませんでした。配色という作業は、私にとってはデザイン画を描くよりもナチュラルで、思い描く世界観にぐんと近づけてくれるものだったのです。
刺繍教室に対する思い

ワッフルを食べた後、お皿に描かれた野いちごの絵をコースターに描くスミレ。
当時の私は、刺繍の技術そのものだけでなく、せっかく覚えたテクニックをどんな場面でどんなふうに使って作品づくりにつなげられるか、その工夫をお手伝いしたいと考えていました。さらに、当時の私は「ハンドメイドの強みは、色合いやサイズ、形や仕様を思い通りに作ることができること」にあると信じていました。だから、決まった課題をこなすのではなく、作りたいものを自由に形にしていくのが一番だと信じていました。
のちにレッスンを重ねるなかで、配色が苦手だと感じる人が多いこと、デザインを自分でアレンジしたいと思う人はそれほど多くないことを知り、こうした考えは少しずつ変わっていくのですが……。あの当時は心からそう信じていて、その思いこそが「ハンドメイドってすごくいいよ!」と刺繍や手作りの楽しさを人にすすめる理由になっていました。
第5回につづく

次回は、私の背中を押してくれた夫の一言のお話です。
刺繍と私の物語
教室のご案内
・刺繍教室の通い方:おけいこ通いの始め方
・最新のレッスン案内:教室からのお知らせ
・ご予約の流れ:ご予約について
・刺繍を仕事にする:認定講座のご案内
刺繍、やってみませんか?
初めて刺繍をされる方には「初心者さん大歓迎」カテゴリもおすすめです。▶︎ 初心者さん大歓迎の記事一覧へ